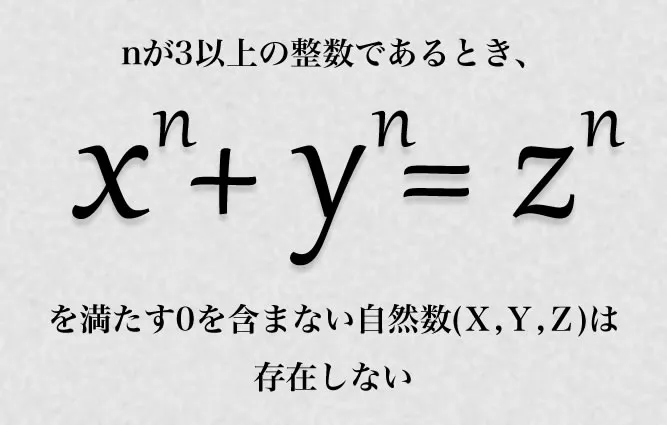 サイモン・シン著「フェルマーの最終定理(2006)」を読みました。
サイモン・シン著「フェルマーの最終定理(2006)」を読みました。
紀元前のピュタゴラス(教団)に端を発し、フェルマーが予想してから350年もの月日をかけて1995年にアンドリュー・ワルズが証明したフェルマーの定理に関する長い数学の歴史の物語でした。
数学が殆ど出てこなくて中身はわからない(勿論出てきてもわからない)ものの、天才たちが集う、奇妙な世界で起きた大発見の興奮だけは十分に伝わってきました。
歴史が深いし、パスカルとかオイラーとか、谷山-志村とか、とにかく関わった人の多いこと!
個人的に気になった一節は、
「”確率の法則”とはよく言ったものである。確率とはあらゆる法則のアンチテーゼではなかろうか」(バートランド・ラッセル)
というフェルマーの定理とは全く関係のないものでした・・。


コメント