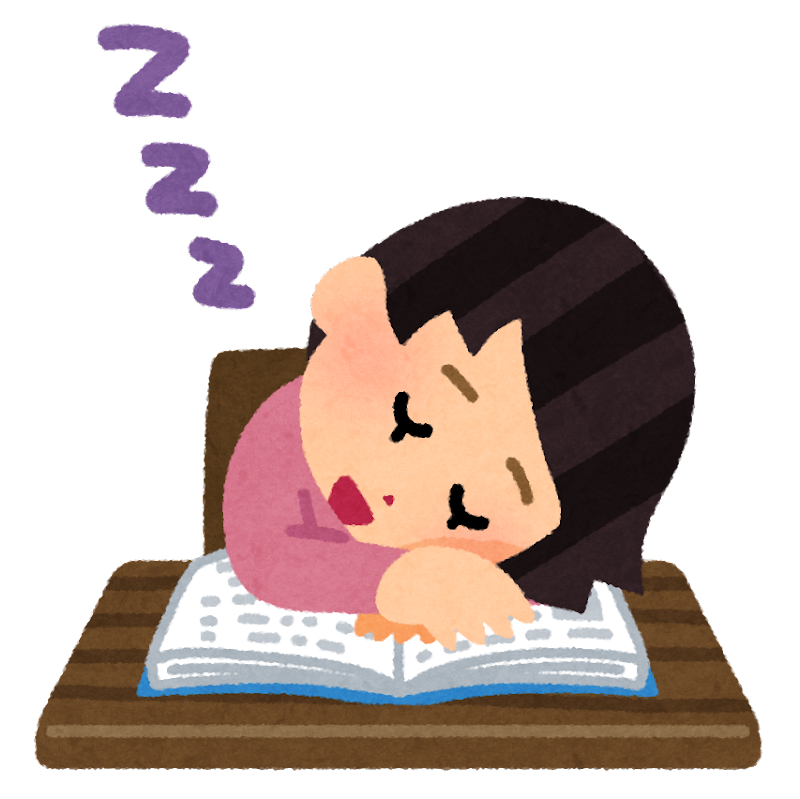
幼き頃に心を悩ませた「私とは一体なんなの?」という疑問に対し、ロボットの研究者になった著者が研究データと思考実験によりズバット答える「脳はなぜ「心」を作ったのか「私」の謎を解く受動意識仮説(2010)前野隆司著」を読んでみました。
結論的には、意識とはエピソード記憶(単なる意味記憶ではなく、時空間的な広がりのある記憶)をするために必要な錯覚であり、クオリア(感覚的体験に伴う独特で鮮明な質感)も脳が見せている錯覚に過ぎず、人間は大きく見ればロボットと変わらない。という内容でした。
妙に初歩的な話から始まり、急に意識やクオリアといった抽象的な事に関する結論を出す辺りはやや極端な気がしましたが、個人的にはとても興味深い内容で、またうなずける部分も多い本でした。
例によって個人的に気になった部分をまとめます。
「私」は何のために存在するのか?
私たち人間の「エピソード記憶」は、高度な認知活動をするために「意味記憶」よりも後で進化的に獲得されたものだと推測できる。
ではエピソード記憶ができるようになるためには、何があればいいだろうか。
答えは「意識」だ。
「エピソード記憶」を持たない痴呆状態の動物がいたとしよう。この動物は、やったことを片っ端から忘れていくようなものだ。だとすると、行ったことを「意識」した直後に忘れるのではなく、そもそも「意識」しなくても問題ない。「意識」したということをどうせ忘れてしまうのだから。「無意識」の小人達が行った「知」の処理の中から、最もやりたいことを選択して実行する「意」の機能や、その時の感情を表現する「情」の機能があれば、別にそれを「意識」していなくても問題ないのだ。
「意識」がないということは「無意識」の小人たちの多様な処理を多様なまま記憶する必要があるということだ。しかし、たくさんのこびとたちの処理は分散し並列に行われている。これを直接エピソードとして記憶しようとしても、膨大で訳が分からないし記憶しきれない。それに、エピソード記憶は、自分が行ったこと、注意を向けたことの記録だ。たくさんの小人たちではなく、「私」ひとりの体験でなければならない。
つまり、エピソードを記憶するためには、その前にエピソードを個人的に体験しなければならない。そして。「無意識」の小人たちの多様な処理を一つにまとめて個人的な体験に変換するために必要十分なものが、「意識」なのだ。「意識」はエピソード記憶をするためにこそ存在しているのだ。「私」は、エピソードを記憶することの必然性から、進化的に生じたのだ。
Tochiの勝手な感想
科学的な実験によると、「自由意志」は単なる錯覚であることが示唆されています。
また、この実験を参考にせずとも、因果応報、つまり原因があって結果が生じる事を信じるのであれば、既に現在には原因が揃っている以上、未来の結果は変えようがない、つまり自由意志なんて存在する余地がないという理屈が導かれます。
実際、人の性格や知能は「遺伝」と「環境」によって決まるとされていますが、遺伝子を自分で選択できないのは仕方ないとしても、環境だって自分で選択できると考えるのは経験的にも極めて怪しい気がします。
また、人には視覚や聴覚、触覚などに、様々な錯覚が存在することが知られていますし、錯覚とは違うけど、動物によっては見える色の種類まで異なる、つまりどの動物が見るかによって世界は全く違って見えるはずです。世界はひとつの筈なのに。
つまり、私達が見ている世界は、私達の外にある世界ではなく、私達の脳の中に作られた世界のバーチャルイメージにすぎないということなのでしょう。
だからといって、意識や自分もすべてが錯覚だと言われても、まー全く納得はできません。錯覚ってそういうものですから(笑)
「意識」や「私」は、覚えておくべき記憶にコントラストを付けるための装置にすぎない。これは中々に面白い発想でした。
とはいえ、全てが自動処理で判断の余地など一切ないのであるならば、コントラストも自動処理にして「意識」や「私」など無くして何が問題なのか?(あったところでどうせ自動処理なのに?)
または、「意識」や「私」を錯覚した結果、自死を選択することの合理性はどこにあるのか?(過剰な知性のアポトーシス?)
などなど、興味の尽きないお話でした!


コメント